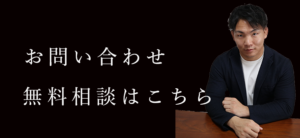大阪市都島区にある土井工務店代表の土井(@takeshidoi73)です。住宅と店舗に特化してリフォーム/リノベーション専門店を経営しております。
最近よくガレージハウスの問い合わせがあるので、予め皆さんにガレージハウスを考えるを作る上での最低限知ってほしい知識について今回は記事を更新します。
先に結論から言うと、自作でガレージハウスを作れるかと言うと、できるかもしれません!が次の条件が必要です。
- 土地を持っている
- 時間が有り余っている
- 工具を使い慣れている
- 汚い作業に慣れている
- 手先が器用
上記に当てはまる人はDIYでガレージハウスを作れる可能性は高いです。
また、初めにガレージハウスは、新築または増築として立てる方法と、使わない部屋の中をリフォームして、インナーガレージにする方法の2点があります。
そして、ガレージハウスを建てる際は基本的に建物としてみなされ、新築、増築の分類にあたり特定行政庁または検査機関による建築確認が必須の場合が多いのでセルフビルドでは基本的に認められません。
そのため、建築基準法に適した条件で、なおかつ建築確認が必要になるケースが多いのが新築、増築で行うアウター部分のガレージハウスです。
逆にリフォームで行うインナーガレージの場合は大規模修繕(200㎡超)などで無い限り、リフォームとして分離されるので建築確認は不要でセルフリフォーム(DIY)ですることが法的に可能の可能性が高いです。
これらを踏まえて、もしガレージハウスを建てるならどのような手順が必要なのか?ということを説明していきたいと思います。
ガレージハウスを建てる前に知っておくべき建築基準法違反になる要件
まず初めにガレージハウスを建てるのに必要なのは建築基準法やその他の法令に適しているかどうか?という点をかく人する必要があります。
実際問題になるのは多くの場合は建蔽率と容積率になってくる場合が多く、このまま建築してしまうと違法建築になってしまうようなガレージになるのがほとんどで、諦めるの人が多いのがガレージハウスでもあります。
しかし、例外もあります
- 柱の間隔が2m以上
- 外壁の連続してない部分が4m以上
- 天井の高さが2.1m以上
- 地階を除く階数が1であること
上記に当てはまった場合、間口や奥行きが1mずつ緩和されるので、これらの緩和制度を利用してカーポートやガレージハウスを考える日が多いのも事実です。
しかし、その反面ガレージハウスの外壁部分は諦めるという人もたくさんいるというのも事実です。
・10㎡以上の建物の建築は原則、特定行政庁(市役所の建築課)に行って図面や申請書類、建築確認が必要
基本的に市役所の建築課に行けば、とても詳しく教えてくれます。
その際に必要なのが、建築予定の図面、検査済証、建築予定の土地やマイホームの謄本をあげていればスムーズに進みますが、ガレージハウスで一番難航になる原因の一つが、検査済証が上がっていないお家。
この場合は、一級建築士による現在のの建物に安全性を確認したとの文言や、建物の安全性の証明が必要となります。
ちなみ僕のお世話になっている先輩が一級建築士なのですが、その方に相談したところ検査済証がない場合、境界の確定までするから費用がえげつないくらいかかる!と言われ、その時のお客さんは照明を発行するのを断念しました。
上記の条件に当てはまっていると何が大変か?というと、建築確認や開発許可をしてもらうのにその書類の審査すらできないといった状況になります。
それ故、検査済証が上がっていないお家は大変なのです。
また、ガレージハウスの建築確認は特定行政庁による建築確認と民間の建築確認の2種類がありますが、基本的にこの部分は一般の方では分からないので、費用を払って工務店や設計事務所に任せる方が無難です。
自分で費用を浮かせようとしても、結局は工事会社や設計事務所が関与する部分ゆえ任せるのが無難です。
・家が防火地域にある場合、ガレージハウスを建てる建築確認は必須
防火地域である場合、建築確認は必須となります。
この自分の地域がどこの地域なのか?という点は、市役所に行き、お金を払えば登記事項証明書を発行できますので、一度確認してみてください。
余談ですが、建てた時は防火地域では無かったのに今は防火地域になっていたというパターンもありますので、建てた時の資料が確実というのはありませんので、建築確認が必要な工事をする場合は基本的に工事をする会社が説明や確認をしてくれます。
DIYでガレージハウスを建てる方法や順序
もし、自分でガレージハウスをセルフビルドするならば基本的に材料や工具を揃えるだけでも100万円超えるような工事になる可能性が高いので、セルフビルドで安く済むといった動画や記事には気をつけてほしいものです。
基本的に増築の工事は耐震性を備えさせる工事としては、大工でないと難易度が高いのが実際の現場です。
これらを踏まえて、どのような工事になるか説明しましょう!
1.仕様および設計を決める(木造or鉄骨)
寸法、図面、電気、水道の有無、仕上げ材、壁材
工事をするのに最初に決めるのが仕様を決めることで、ガレージハウスだけでなく木造でも最初に決めることは、木造にするのか鉄骨にするのか?といった点です。
個人的には、素人の方のDIYであるのであれば、鉄骨で柱を組むのは不可能なので木造を推奨しています。
※木造の場合、耐震上の問題で横縦や縦共に幅は3mから4mごとに柱が必要なので、耐震上の問題として真ん中に柱が欲しくない場合、3.5m前後が幅としてとれる間口の限界になるでしょう。
図面なんて書けないという方も多いでしょうが、せめて何の材料を使うかというプランは用意して簡単で良いので寸法を作っておくと作業をするのに非常に効率が良いです。
ちなみにですが、普通は電気図面や木工事(大工)の図面、平面図や立面図、完成イメージまで作っておくのが基本ですが、ベテランの職人たちは図面なしで工事をしてしまうというのも多いのが実際の現場で、当社もお客さんの予算次第では図面なしの工事もありえます。
また、プロでも打ち合わせと設計を含めて工事期間は1ヶ月から2ヶ月必要なので、一般の方のDIYであれば4ヶ月から6ヶ月を想定しましょう。
2.木造の場合 最初の工事手順

基礎を作る際、型枠(パネコートorコンパネ12mm)を組んでコンクリートで流し込むか、束石を使って在来の軸組工法で行くのか、コンクリートブロックを積むのが有効。
まずは土台を作っていくことから始めましょう!ちなみにですが、その土台にセメントを流し込んだり、鉄筋を入れるのでコンクリートのブロック塀を積む場合は、下の土が水平であるか?という点にも気をつけましょう。
また、ブロックを積む場合でも業者は捨てコンといって、土台となる部分が水平になるようにコンクリートを流し込んでいます。
上記の写真はモルタルですが、コンクリートはセメント2,砂1,砕石1の分量と水で混ぜて作ります。
捨てコンであれば、上記のようなモルタルでも構わないので必ずセメントは流すようにしましょう。
3.土台の加工 (耐震に影響します)
土台を入れて、柱を立てるために穴を開けて、先端にホゾを作り、金物やアンカーボルトで耐震補強を行っていく。
簡単に文章にしていますが、大工仕事になりますので難易度は高くなります。
専用に機械または手鋸や丸鋸での加工が必要となります。
4.建前(棟上工事)を行い、柱や梁、火打梁、筋交を入れていく

建前を行う際は、一人では危ないので必ず2人以上で作業を行いましょう。
また、この作業は耐震性にも関わってくるので本当を言えば大工が必須の作業にもなるのですが、DIYでする場合は寸法を材木屋さんに依頼して加工するのも一つかもしれません。
また、必要に応じて足場を用意する必要があります。
当社は一階までの建物であれば、身動きが取りやすいか取りにくいかという判断も踏まえて足場を建てないという判断もしますが、原則3m以上は一般の人では怖い高さなので注意しましょう。
5.天井の下地

桁の上に母屋を作り、垂木を455mm間隔で打っていく、この際に勾配を予め決めておき、図面を作っておかないと要領が悪くなるので注意しましょう。
上記の木下地が完了してから針葉樹合板(コンパネ)12mmを打っていきます。
最後に屋根のルーフィング(防水シート)を引いていきタッカーで打っていけば屋根の下地は完了です!
水道、電気等の設備関係
電気及び水道の引き込みを行います。
後付けでガレージを増築する場合は、住宅から引き込んでいる電気を分電盤から単独で引っ張り、水道もまた住宅の中の水道をチーズで分岐してお湯と水道の配管を引っ張ると良いでしょう。
そして、どの配管や電線を壁や床に仕込んでおきましょう
また、電気は分岐では無く分電盤から単独で2.0mmでひっぱておく必要があるので、第二種電気工事士の資格のある職人に依頼し、設備関連もまたは自己責任で大きな事故につながるので、有資格者に依頼してください。
外壁の仕上げまでの流れ

壁材(コンパネ12mm)を貼って、透湿シートを貼り、必要に応じて胴縁を打っていくまでが下地の作業となりますが、あらかじめ外壁の仕上げを決めておきましょう。
- サイディングまたはトタン
- ラスカットを貼って、左官して塗装をする
- タイルを貼る
全て難易度が高いですが、一番簡単なのはトタンを貼ることなので、それも検討してみるのも一つの手段だと思います。
内装を仕上げていく

床や天井を仕上げる天井には寸三(35×35)を使い天井にはケイカルを貼るのが推奨(外部面なので、クロスは、基本的に不可)。ケイカルに塗装するのがおすすめ
床は左官仕上げがおすすめ、車やバイクを置くところなので、割れる可能性があるので最低でも10cm以上は打っておきたい。
この際に量が多くなるので、自分で練るとしんどいので、生コン車を呼んで流してもらうことをお勧めします。
内壁には下地を木工事で行った後に壁に12mmのコンパネやボード、ケイカルを使用。
外部なので不燃性の高いケイカルを推奨しています。
ボードは割れる恐れのあるので、理想を言えばコンパネのような分厚い下地の上にケイカルを貼るのが理想です。
最後に外部なのでクロスではなく塗装をすることを当社では推奨しています。
要らない部屋をリフォームでインナーガレージにすればDIYで作ることは可能
このような建築確認をせずに済む方法は、基本的にはガレージの最低限の広さを求めるのであれば実際問題難しいんですよね。
そのために建築確認をしないで済む方法となると、小規模の改修工事、つまりリフォームでインナーガレージを作ると言う選択肢が挙げられます。
その際は内装工事の内訳としては、解体工事と大工工事がメインとなりますが、お客さんは使わなくなった部屋を再利用できた、作って良かったと言う意見もあったので意外と良いのかもしれません。
その際の記事が下記なのでインナーガレージもアリかな?と言う方は読んでみてください。

締め:自作DIYでガレージを作るなら、建築確認がいらない小規模の リフォーム工事の範囲内でするべし
結論、建築は法律が厳しいので簡単なDIYであればガレージハウスというよりは、雨が濡れないような囲いを作るようなイメージの方がいいのかもしれません。
実際問題、建築基準法非違反した建物を建築すると工事会社及び施主にも責任は及びます。
そのため、難しいかもしれませんが室内のリフォームのようなDIYに挑戦してみてはいかがでしょうか?
皆様が少しでも素敵な時間をお家で過ごせるよう願っております。
質問や相談等があれば、記事を読んでくれた方に費用等はいただいておりませんので、気軽にご連絡ください。
それでは時間を大切に良い一日を。
土井工務店 代表 土井健史