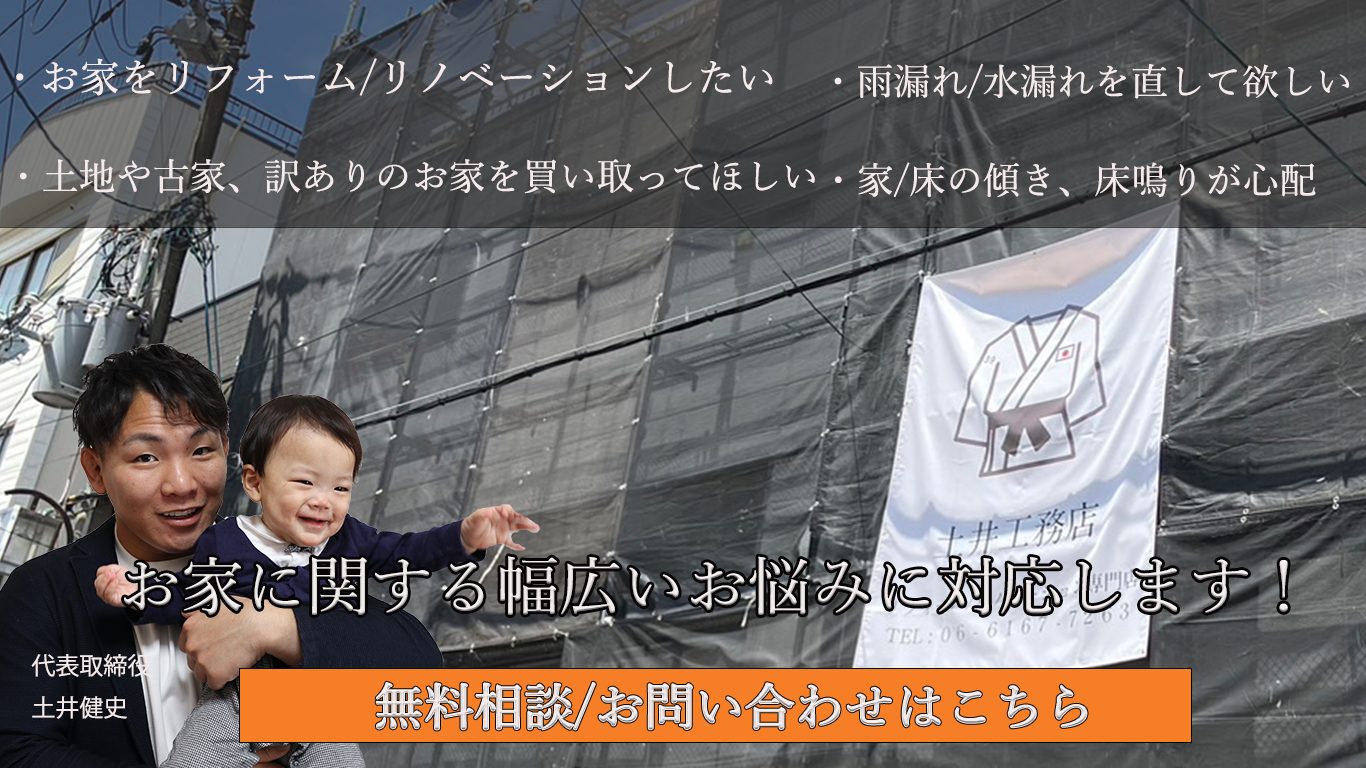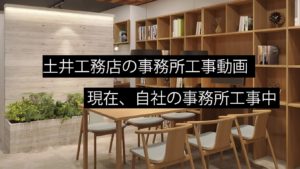大阪市都島区にある土井工務店代表の土井(@takeshidoi73)です。
住宅と店舗に特化してリフォーム/リノベーション専門店を経営しております。
大阪市生野区にある寺田町駅すぐ近くのお家のお客様から連絡があり、家の水漏れが止まらない!直してくれ!という問い合わせと連絡でした。
問い合わせ後すぐに水漏れ箇所及び原因を特定すると、今回の水漏れの原因は給水の水道配管の凍結が原因でした。
急な寒波が近畿地方に来たため水道が凍って、水の圧によって塩ビの水道管が破裂していました。
今回水道管が破裂したことにより、生じた水漏れで行ったリフォーム工事は次のとおり
- 解体工事、天井・壁(水漏れ箇所を探すため)
- 破裂した古い水道の給水配管の撤去
- 新しい給水配管新設工事
- 壁下地リフォーム工事+断熱工事
- 天井下地リフォーム工事+断熱工事
- 電気照明新設
- クロス張り替え
想像するだけでも時間とお金のかかるような工事です。
特に大変だったのが、電気照明の傘に水が貯まるほどの水漏れを起こしていたこと、天井の下地や壁の下地が水に濡れて下地が弱っていたことが今回の工事で大変だった場所です。
また、今回のリフォーム工事は給水配管の水漏れであったため、近隣の方が元栓を閉めてくれました。
空き家の状態であったため、近隣の方が給水栓を閉栓していなければもっと大変なことになっていましたね。
もし、あなたの家が水漏れをしているようであれば“水道の元栓メーター”のところに行って、元栓を閉めてください。
水道の給水側の水漏れは元栓を閉栓しない限り一生水が止まらないので大変なことになりますから。
水道メーターの場所は
マンションや団地は、廊下の各部屋メーターがある扉の中
一軒家の場合は、家の周囲の地面にメーターボックスが分厚い蓋がされているものです。
基本的に水の閉栓はバルブを開ける、締めるなどの言い方をします。
時計回り=締める
反時計回り=開ける
これだけは覚えておきましょう。
さて、今回は水漏れをしたことによって必要になった工事について紹介していきたいと思います。
もし、読者の方のお家が水漏れした時に内装リフォームはどのような工事をするのか?
具体的なイメージが今回の記事で学ぶことができるでしょう。
凍結して割れてしまった給水配管の状態

塩ビの給水の配管が根本から破裂していました。
原因は2023年の1月大阪に寒波が到来したことが原因です。
この塩ビの配管は洗濯機の給水栓であったのですが、生野の町並みにある昔ながらの古いお家で2階まで続く長い給水栓の配管が伸びていました。
また、このお家は隣と壁が一体になっている連棟(テラス)と呼ばれる物件なのですが、なぜか一階を超えた2階部分だけが繋がっておらずに配管の箇所が壁から浮いていました。
そのため、寒さがモロにこの配管に直撃して給水の配管を凍らせました。
また、このお家は現在の使用状況は倉庫であったため給水栓も長い間使用されていなかったようですね。
結果的にこの配管の水漏れというより、破損部を見つけるために一階の天井を解体して、壁を解体したため、それを復旧するための大工による内装リフォームが必要となりました。
しかし、破損部を全部とると解体を全部する必要があるため、水漏れした配管を上記の写真のように切って、新しい配管を上に伸ばして断熱処理をしようという施工になりました。
ちなみにこの流れで工事ができたのは、解体をしたことによって破損部が根元の給水栓付近ということがすぐに判明したからできた工事でした。
解体した壁の下地を大工がリフォーム工事

壁を解体すると、見ての通り奥の家から風がいくらでも入ってくるので、室内もとても寒かったのがこの現場でした。
もちろんですが、断熱材などなし、隣の家との壁には穴があります。
そのため、どうせ復旧するならこのメチャクチャな壁の下地を直して、断熱材を入れる工事になったのが今回の工事です。
余談ですが、このお家は基礎もまともになかったので、耐震性・断熱性に欠けている家でまさに旧耐震の手抜き工事のお手本のような家でした。
今回の内装工事のこだわった点は次のとおり
1.下地を頑丈にするため、柱の補強、下地のやりかえ
2.断熱材にグラスウール100mmを使用
3.隣の家が境界にある壁は全て木材(コンパネ)を使って、石膏ボードを使わない
なるべく木材も等級の高い質の良い木材を使って、少しでもお家が長持ちできるような工事をすることに決めました。

最初の壁下地と見比べてどうでしょうか?
反対の家まで見えていた壁を大工が内装リフォームをしたことによって、隙間風がこれだけでも減りました。
また、木材も柱及び下地を新設しているので、耐震性や強度も上がっています。
もはやリフォームというよりは、リノベーションと言っても過言ではないほどの質の高い工事になりました。
また、天井下地も水に濡れて下地が弱くなっていたのと、古い下地であったため強度を上げるために大工が内装リフォームを行いました。
というよりは、工事したのは筆者である僕ですw
「大工の仕事、天井の内装リフォーム工事」

左がリフォーム前、右が天井下地を寸三(35×35)の木材を使って天井下地をつくりました。
驚いたのが、リフォーム前の電気の傘から大量の水が落ちてきて僕が濡れたことです。w
大工工事をするはずなのに、水に濡れるという不思議な現場でした。
また、このリフォーム工事をするときに苦戦したのが、昔ながらの古い生野区の家に限らず、下地の寸法や基準が滅茶苦茶なので工事が難しいんですね。
大工というのは、下地と壁面の水平を見て、あらゆる角度から調節して、全ての下地を見ていると言っても過言ではありません。余談ですが、僕の師匠は70歳になりましたが良い仕事をします。
今回の天井下地では、僕自身の工事に加え師匠のアドバイスもあって本当にいい天井下地ができたと思います。
最早、リフォームというよりかは性能が上がって新築並みの下地なので、リノベーションといっても過言ではないでしょう。
リフォーム工事の完了と凍結の対策に断熱工事

これが下地の仕上がりです。
最初は風が吹いて寒い廊下だったのですが、むしろリノベーション工事をしたので水漏れする家の状態より、強い家になりました。
今回のリフォーム工事の序盤に解体をして感じたのは、生野区の古い建物だけかもしれませんが、下地がめちゃくちゃで耐震性は低いなと感じました。
もちろん旧耐震時代の建物ですが、壁が5.5mm厚の材料を使い、下地は大きな間隔(455mm)に胴縁を一本だけ入れるといった今では完全な不良工事です。
普通であれば壁は12mmを使い、下地も最低でもマンション間柱の27×40を使って欲しいものです。
余談ですが、胴縁を使うのであれば最低でも材料同士の感覚は300ピッチ間隔にしておくことを推奨します。
ちなみに僕の師匠は、この家の元々の工事は手抜き工事の部類ではないかな?と工事をしていて仰っていました。
僕は平成生まれなので、昭和時代の工事がわかりませんが師匠曰く、俺の時代でもこれは手抜き工事や!と言って怒っていましたので。w
本当に大工という職人の仕事が好きなんでしょうね。
締め:水漏れは怖い
さて、みなさんこの記事を読んでどのように感じたでしょうか?
今回の水漏れをきっかけにこの工事は内装をリフォームすることになりましたが、所有者の方は下地が滅茶苦茶であるなんてことはもちろん知りませんでした。
そのため、水漏れで落ち込むのではなく、開き直って悪いところをリフォームできる、治すことができると心機一転することがいいですね!
今回の工事内容は次のとおり
1解体工事
2水道工事
3内装リフォーム工事
4電気工事
5クロス張り替え工事
生野区の現場は小さな水漏れをきっかけにとても大きなリフォーム仕事になりました。
ちなみにですが、水漏れは放っておくともっと木材を腐らせるので、放置しておくと本当に大変なことになります。
ですが、もし自分の家が水漏れした場合、一番怖いのは”下地が腐ってしまう”ということ。
お家は人の体と一緒で、早期発見、早期医療が一番安く収まって、いいんですよ!
実際水漏れも放っておけば置くほどお金がかかるので、水漏れはすぐに対応することをお勧めします。
もし、家の屋根の状態書きになる、自分の家も古いから一度見て欲しい、雨漏れをしている気がする、水漏れしている気がすると言った方は一度当社にご連絡ください。
皆様が少しでも素敵な時間をお家で過ごせるよう願っております
質問や相談等があれば、記事を読んでくれた方に費用等はいただいておりませんので、気軽にご連絡ください。
それでは時間を大切に良い一日を。
土井工務店 代表 土井健史